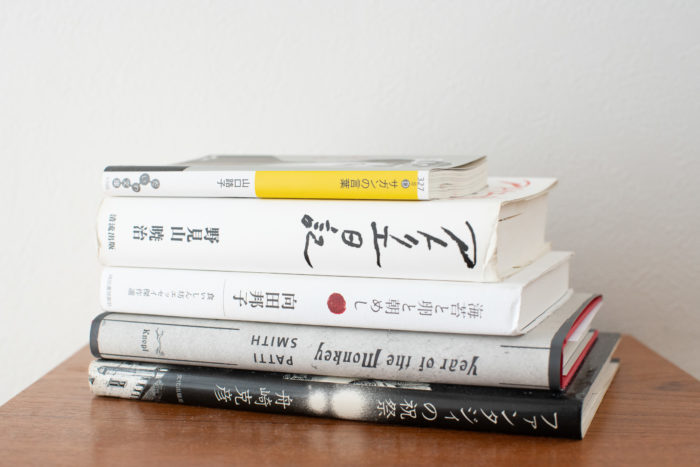ここ数年、EPのリリースが続いていた湯川潮音。7年ぶりというフルアルバム『10の足跡』は、湯川を通じて世界に触れ直すような感覚を覚える作品だ。音にふれること、声を出すこと、音を声を重ねること──このシンプルな行為がどれほど発見に満ちた喜びであるかが聴き取れる。
湯川が得意とする、ギターとソプラノヴォイスの響きを軸にしたフォーキーで幻想的なサウンドに加え、フィールドレコーディング、多重録音、管楽器のアンサンブルによってかたちづくられる物語はさまざまなトーンに彩られ、懐かしくも新しい。初めてセルフプロデュースで取り組み、プライヴェートでは出産・子育てというハードモードをこなしながらたどり着いたという本作について訊いた。
聞き手:丹野 未雪 写真:品田 裕美 ヘアメイク:森 愛
【後編】前編(2022年9月16日(金)公開)はこちら

【後編 全曲解説】
1.ポーラ
──新しい予感に満ちた曲ですね。コーラスの幸福感と、関島岳郎さんのソプラノリコーダーが愛らしい。
ふふふ(笑)。曲と歌詞の印象は真逆かもしれません。「ぼけますから、よろしくお願いします。」という老老介護を描いた映画からインスパイアされた曲です。続編が今年公開されていて。子育ても介護も、ある意味、自分を差し出すことというか。子どもが右に行きたいって言ったら、左に無理やり連れて行けないし。愛があるだけでは済まないようなものも見るし、見たくないものまで見るし。この映画のなかで、「なにもしてあげられなくて、ごめんね」っていう台詞があって、それがすごく心に刺さったんです。自分も子育てに何もかも捧げているのに、どこまでやってもまだ足りないって感じることがある。終わりが見えない日々の闘いっていうか、そんなことを唄った曲です。
──歌詞の前半で、「新しい名前を付けてあげる」と言っていた語り手が、後半「貴方に呼ばれる名前で生きよう」と、立場が反転する展開は新鮮でした。
父にも母にもなるし、明日はお姉ちゃんになったり、きっと何役もやらなければいけないし、それについていかなきゃいけないんですもんね。
2.枯葉
──水面を揺らすような管楽器の軽快かつ重層的なアレンジが印象的です。こちらは歌詞と曲が同じ色彩という感じがします。
素直に展開させればフォーキーな曲だけど、管楽器がうねっていることによってエキセントリックというか。曲ができたときに、これはヤマカミヒトミさんだな!と思ってすぐ依頼しました。管楽器のアレンジはやったことがなかったので、栗コーダーの栗原正己さんに相談したりしましたね。この曲はブリジット・セント・ジョンの影響もちょっと受けています。彼女のフォーキーなアルバムをピンク・フロイドで知られるロン・ギーシンが編曲しているものがあって、そのアンバランスな影響が面白かった。歌詞のせいか、時期のせいか、「戦争の歌ですか?」って聞かれることが多いんですけど、その影響も少なからず受けていますが、書き始めは老いるということについて考えた曲なんです。自分の体も心も変化していくなかで、幼い存在が身近にいると、同じものを見ても視点がまったく違う。歳をとることは経験が増えるし尊いことだと思うんですけど、同時に切なさもあるというか。

3.誰がつけただろう
──佐藤綾音さんのサックスが素晴らしいですね。
綾音さんはマヒトさんの紹介です。マヒトさんも付き合いが長いので、求めているものをすぐ察知してくれて。スタンダードにやったら、ギターとストリングスのアレンジが浮かぶと思うんですけど、あえて管楽器でやりたくて。後半に雄叫びのようなサックスが入ってるんですが、それも一発録りで。綾音さんはとても面白い人でした。
──「わたしもわからないということにしがみつく」。こうした一節に、これまでにない生々しさを感じます。
「しがみつく」というのも、気になっていた言葉です。今、この曲のMVを『わたしの子守唄』(2018年)のデザインをしてくれた、本田千尋さんが作ってくれていて。歌詞の言葉がシンプルなんですけど、まさに子育ての影響があると思います。子どもといると常に「なんで? どうして?」って質問責めで、自分の見方とか考え方にしても、今まで当たり前だと思ってきたことに対して「なんでだろう?」と思うようになってきて。ある日、二人でご飯食べながらニュースを見ていたら、ウクライナの男の子がお母さんがいないと泣きながら国境を越える映像が流れたんです。うちの子が、「なんであの子ママいないの? なんで普通の道なのに、あそこから先に行くと安全なの?」って言われたことを書き留めた曲です。
4.バースデー
──アイリッシュなテイストがふんだんに盛り込まれた楽曲です。ファゴットが効果的ですね。
マヒトさんのアイデアなんです。どうしても使いたいということで、オーケストラで活躍している中田小弥香さんにお願いしました。これはニューヨークで書いた曲で、ずっと歌詞がないままだったんです。バースデー、子どもの誕生日のことを思って歌詞を書きました。出産はもちろん壮絶な体験だったし、生まれたばかりの喜びも覚えているし、でも歌詞を書き終わってみたら、それだけじゃない物語のことを書いてるような気もしてきて。地獄のような苦しみも、天にものぼるような喜びも日々あって、生まれ変わっている。バースデーは人生で一度きりのものじゃないなって考えるようになって。
──楽曲にも歌詞にも童話の冒険譚のような雰囲気が漂いますが、孤独が色濃く感じられますね。
あらためて聴き直してみると、舟を漕いでいる人は自分のことだったのかな、って思ったり。前が見えなくて落ち込んだ時期、やっぱり人に会うことで救われるというか、生きることで癒されるというか。
5.あなたの国へ
──バンジョーとマンドリンが軽快に跳ね、フィールドレコーディングの鳥の声に木の枝と、楽しい楽曲です。
わたしの曲にはめずらしく(笑)。遊び歌というか。公園で子どもが拾った木の枝や石が山のように溜まっていくので、それを鳴らしてみました。この「カカカカカ」っていう音はキツツキの声なんですけど、友人の松岡三千代さんが山登りをしたときに録ってきてくれて。
──口ずさみやすい曲ですよね。
でもこの曲、大恋愛の歌なんです。
──えっ! てっきり、お子さんとの遊びのなかで出てきた曲かと思っていました。
子どものことは1ミリも考えなかった(笑)。過去の話ですけど、すごく好きな人がいたときに、あなたのことがすべて知りたい、あなたに住み着きたいって思うほどの感情になるけれど、知っても知り尽くせない、あなたにはなれないという、気持ちを思い返して作りました。