
ここ数年、EPのリリースが続いていた湯川潮音。7年ぶりというフルアルバム『10の足跡』は、湯川を通じて世界に触れ直すような感覚を覚える作品だ。音にふれること、声を出すこと、音を声を重ねること──このシンプルな行為がどれほど発見に満ちた喜びであるかが聴き取れる。
湯川が得意とする、ギターとソプラノヴォイスの響きを軸にしたフォーキーで幻想的なサウンドに加え、フィールドレコーディング、多重録音、管楽器のアンサンブルによってかたちづくられる物語はさまざまなトーンに彩られ、懐かしくも新しい。初めてセルフプロデュースで取り組み、プライヴェートでは出産・子育てというハードモードをこなしながらたどり着いたという本作について訊いた。
聞き手:丹野 未雪 写真:品田 裕美 ヘアメイク:森 愛
【前編】後編(2022年9月17日(土)公開)はこちら

──初のセルフプロデュースということですが、どのような経緯があったのでしょうか?
曲作りの流れから自然にそうなっていったというか。家でひとりでギターを弾き語りしながら曲を作るということがほとんどだったんです。コロナ禍ということもあって、会うにしても限られた時間のなかで自分のイメージを伝えていかなくちゃいけない。言葉だけじゃなく、音を聞いてもらったりして具体的に伝えていたら「もうやりたい方向もビジョンも固まっているなら、プロデューサーいらないんじゃない?」って。
──ビジョンはいつぐらいからはっきりしてきたんですか?
今、子育て中なんですが、妊娠も出産も想像していた100倍以上も大変で。音楽活動だけじゃなく、自分のことはなかなかできない状況だったんですけど、そのおかげでずっとためていた思いが熟成したというか。
──焦ったり、もどかしくなかったですか。
もどかしかったです、本当に。落ち込みましたし、体調を崩したりもして。でも、人に会えない時間が増えていくぶん、映画や本でもドキュメンタリーに関心を持つようになったんです。小さい「人」…子どもを見つめる時間が長かったこともあると思うんですけど、人間に興味を持つようになったというか。日常的な心の動きとか、そういうものにふれると安心したというか。
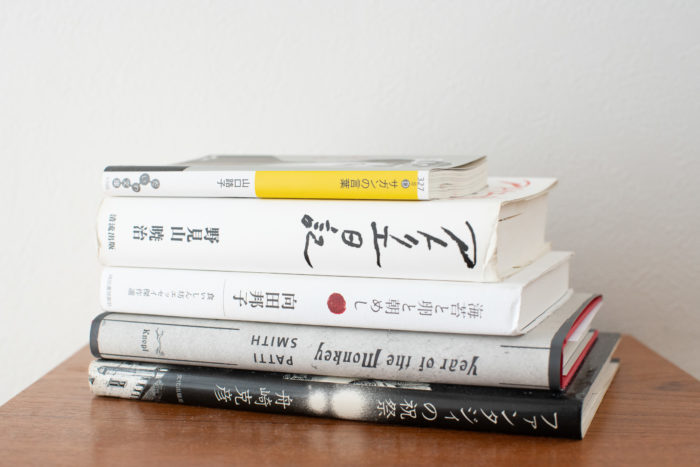
──人間への興味というのは?
すべての人にはその人が主人公の物語があるじゃないですか。その人次第でその物語が変わっていく。誰にもふれられない物語を、すべての人が持っているんだなと。抗うことができない大きな時代の波のような出来事もあるし、個人ではどうしようもないものと闘わなくちゃいけないこともあるけど、自分が主人公であることは変えられないし、変えちゃいけないと思う。
──『灰色とわたし』(2008年)リリース時に書かれた湯川さんのレコーディング日記に、「わたしはやっぱり物語があるアルバムが好きだ」とあります。今作のアルバムタイトルには「10人の人間を主人公にした物語」という意味が込められているそうですが、制作プロセスにおいて「物語」はどういう位置にあったんでしょうか?
これまで「人」にフォーカスすること自体少なかったと思います。もっとふわっとしたものを書いてきたので。ニューヨークに住んでいた頃に書きためていて、『濡れない音符』(2013年)や『セロファンの空』(2015年)にも収まりきらなかったタイプの曲があったり。その後も曲は書いていたので、曲はあるんですけど、破片ばかりが増えていくような感じでした。言葉もパズルみたいに断片はいくつもあるんだけど、つながらないという。ずっとうまくいかなくて。

──湯川さんが歌詞で描く世界は、トーベ・ヤンソンが描く奇妙な生き物たちの寓話的な世界だったり、舟崎克彦が描く動物や植物と対等に対話するファンタジー世界、英米のフォークシンガーの内省的なリリックにルーツを持っていますよね。近年は内省的な歌詞に軸足を置いてきたように思いますが、今作では寓話的な世界が再び顔を覗かせたように感じました。
原点返りはあるなと思いますが、変化してもいるので、どんなバランスで出ているのかな…自分では意識していません(笑)。実は、ずっと歌詞が書けなかったんです。それが、なぜかここ数ヶ月で一気に書き上げてしまったんですよ。「人」というものにフォーカスを当てていったら、雷に撃たれたかのように書けてしまって! 遠回りになった道で、自分が過ごした時間、見ていたもの、吸収したものが影響したのかなと思う。シンプルな曲だし、歌詞もシンプルにしようとしていたんですが、結果的にそうじゃないほうに行きました。
──曲と歌詞が嵌まる瞬間があるんですね。
たとえば映画だったら90分、120分という限られた時間のなかでひとつの世界、ストーリーがあるように、音楽には3分のなかに物語をおさめていますよね。俳句じゃないですけど、そういう形式の美というか、削ぎ落としていくことで粒立つものを表現する魅力というのが曲作りにはあるので。
──人とも会わなくなりましたが、ホール、ライブハウス、カフェといった空間との出会いも減りましたよね。音楽制作に影響はなかったんでしょうか。
それは大きなことですよね。もちろんそこにいるお客様から受ける影響も大きいんですけど、わたしの場合、自分の声や楽器を鳴らしたときの響きから紐解いていくことが多いので、その機会がなくなってしまうのは、何かが一時停止してしまうという感覚はありましたね。唄っているとき、声の響きを感じているとき、ちょっと時空がずれるような感覚というか、日常と離れる瞬間があって。それは第六感的なところなんですけど。そこがうまく作用すると曲ができる気がします。それを思い出すために、道端とか公園で唄ってみたりしてました(笑)。
──屋外で?
自然の中で。今回、フィールドレコーディングをしていて、鳥の声、風の音も入っているんですけど、今回のアルバムにはそういう意味で空間が影響しています。